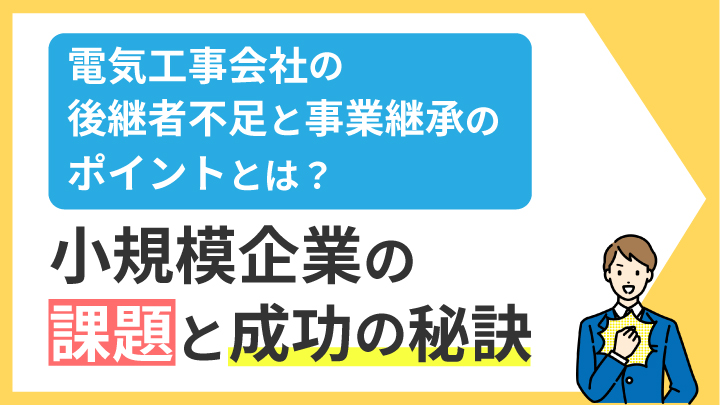2025.10.10
電気工事士の資格取得に使える助成金・補助制度とは? 企業が活用すべきポイントを解説
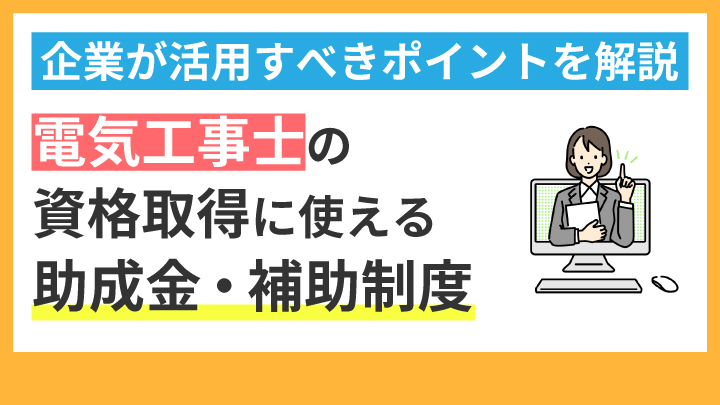
人手不足が続く電気工事業界において、有資格者の育成は今すぐ取り組むべき課題の1つです。
とはいえ、研修費用や教育にかかる負担がネックとなり、社内での資格取得支援に踏み切れない企業もあるでしょう。そんなとき活用したいのが、人材開発支援助成金をはじめとする公的制度です。
本記事では、助成金制度の活用メリットや申請の流れ、注意点に加え、実際の活用事例を解説します。
CONTENTS
電気工事士の資格取得に助成金は使える?
電気工事士資格の取得には、企業が利用できる助成制度があります。
中でも厚生労働省が管轄する「人材開発支援助成金」は、社内での人材育成に取り組む中小企業を中心に活用が進んでいます。
これは、社員の職業能力開発を目的とした研修や教育に対し、賃金補助と経費補助の両面から支援が受けられる制度です。中小企業向けの優遇措置も用意されています。
電気工事士の資格取得においても、対象講座を受講し、所定の手続きを済ませることで申請が可能です。
一方で、名称が似ているものに「教育訓練給付金」があります。これは従業員個人が自発的に利用する制度であり、企業が申請できる制度ではありません。混同しがちですが、明確に区別しておく必要があります。
なぜ今、電気工事士の資格支援に助成金が注目されているのか
電気工事業界では、若手人材の採用と定着が年々難しくなる中で、「自社で未経験者を育てる」必要性が高まっています。
しかし、資格取得にかかる費用や講習への参加時間は、企業側にとっても負担となるのが実情です。
そこで、「助成金を活用して負担を軽減しつつ、戦力を育てる」という選択が、中小企業を中心に注目を集めています。
助成金は単なるコスト削減策ではなく、採用後の定着施策としても有効な手段。制度を上手に使うことで、将来の人材不足への備えにもつながります。
▼電気工事士の資格取得支援は、単なるスキルアップ施策ではなく、若手の定着や育成体制づくりの一部です。若手が定着しない根本的な理由や、育成を仕組み化する考え方については、こちらの記事で詳しく解説しています。
人材開発支援助成金とは? 制度の基礎知識
人材開発支援助成金は、厚生労働省が実施する制度で、企業が従業員に職業訓練を実施した際、その費用の一部を助成する制度です。特に中小企業にとって、資格取得や研修にかかるコスト負担を軽減できる有効な支援策となります。
本制度は、講座の事前申請や対象条件を満たす必要がありますが、電気工事士試験の対策講座なども、条件次第で対象となるケースがあります。
ここでは、制度の基本的な仕組みと注意点を解説します。
制度の概要と対象企業・講座の条件
人材開発支援助成金の対象となるのは、「雇用保険適用事業所」であり、かつ対象となる講座が指定要件を満たしている必要があります。
たとえば、電気工事士試験対策講座の中でも、厚生労働省の定めた特定訓練コースや、指定教育訓練機関による講座であることが条件となるケースが多いです。
中小企業には優遇措置があり、支給率や対象範囲が広がるため、制度を活用するメリットはさらに高まります。
支給対象となる費用項目と金額の目安
助成金の支給対象となる主な費用には、以下の2つがあります。
・講座の受講費用(研修実施経費)
・研修期間中に支払う賃金の一部(賃金助成)
たとえば、電気工事士対策講座を受講させた場合、研修費の60%が助成された事例があります(後述)。また、受講中に支払う賃金についても、1時間あたり数百円の助成が受けられます。
制度活用における注意点と落とし穴
最大の注意点は「事前申請が必須」という点です。助成金は講座を実施してから申請することはできず、受講前に計画書を提出し、認定を受けておくことが絶対条件となります。
また、講座が制度対象外であったり、申請期限を過ぎていたりすると、助成が受けられない可能性があります。
実際に「申請のタイミングを逃してしまい、全額自己負担になった」というケースもあるため、制度の活用にあたっては、事前のスケジュール確認と、厚生労働省や委託機関への問い合わせが重要です。
電気工事士資格で実際に活用された助成金事例
ここでは、実際に助成金を活用した企業の事例と、その成果についてご紹介します。
社員に第二種電気工事士を取得させた中小企業
厚生労働省の「人材開発支援助成金活用例集(特定訓練コース:若年人材育成訓練)」によると、ある中小電気工事会社は、助成金を活用して県立訓練センターの「第二種電気工事士(技能)研修」を受講しました。
訓練時間は18時間で、受講料は36,000円。助成金としては、36,000円の60%相当(21,600円)と、賃金助成18時間×960円(17,200円)、合計38,800円が支給されています。
同資料では「講習を受講させることで即戦力となる人材の育成に役立った」「第一種電気工事士資格取得のための研修も検討する」旨が、助成金の活用効果と今後の展開として記載されています。
成果の波及効果:教育制度としての定着と離職防止
上の事例にもあるように、助成金を活用することで単なる資格取得支援にとどまらず、「教育制度としての整備」「若手定着の促進」「社内の技術体制の強化」などの波及効果が期待できます。
同資料では、電気工事以外の業界でも「人材育成への積極的な取り組みが、従業員のキャリア形成や職場定着、企業経営の安定につながる」といった声が掲載されており、制度活用の有効性が裏付けられています。
助成金申請の流れと必要書類の準備
助成金制度を活用するには、事前の計画と丁寧な申請手続きが欠かせません。
特に「人材開発支援助成金」は、要件を満たしていても事前の届け出がないと支給対象外になるため、制度の流れを正確に理解しておく必要があります。
ここでは、申請手続きの全体像から、よくある申請ミス、スムーズに進めるための外部支援の活用法まで、実務的な観点から解説します。
申請ステップ
人材開発支援助成金のおおまかな申請ステップは次のとおりです。
1.事前準備(講座選定・計画書作成)
まずは自社の教育目的や対象者に合った講座を選定し、「訓練実施計画書」を作成します。
2.管轄労働局への「訓練実施計画届」の提出
原則として、講座開始の1ヶ月前までに提出が必要です(管轄労働局により異なる場合があります)。
3.講座の実施と記録の保管
講座受講中は、出勤簿・賃金台帳・カリキュラム・受講証明書などを適切に保存します。
4.訓練終了後の「支給申請書」提出
受講完了後、賃金助成や講座費用に関する必要書類をまとめ、期限内に提出する必要があります。
5.支給決定と振込
審査を経て、支給決定が出ると企業口座へ助成金が振り込まれます。
申請でよくあるミスの防止策
申請する際にありがちなミスとして、次のようなものが挙げられます。
・計画届の提出期限を過ぎてしまう
・賃金助成対象期間の給与計算を間違える
・証憑が不十分であったり、異なる様式の用紙を使ってしまう
・講座が対象外(指定教育機関でない)であった
提出期限や様式要件は地域の労働局により異なるため、必ず自社のある地域の労働局の要件を確認するようにしましょう。
「自社で申請業務を行うのは時間的に難しい」という場合、社会保険労務士(社労士)や助成金専門のコンサルタントを活用する方法もあります。
なお、最新の申請様式や制度概要については、厚生労働省の公式サイト(人材開発支援助成金ページ)で確認ください。
人材開発支援助成金の申請・活用でよくある質問
人材開発支援助成金は、中小企業にとって非常に有効な人材育成施策ですが、「他の制度と何が違うのか?」「何人まで対象になるのか?」といった疑問を持つ方も多いようです。
ここでは、現場の担当者からよく寄せられる質問とその答えをQ&A形式でまとめました。
何人まで助成金が使える?
人材開発支援助成金には人数の上限はありません。ただし、訓練の内容や事業計画、予算の範囲によっては、全員が対象にならないケースもあります。
実際の適用可否については、事前に労働局に相談することをおすすめします。
助成金は毎年申請できる?
はい、毎年の計画に基づいて申請することが可能です。
ただし、年度ごとに訓練計画を立て、事前申請を行う必要があるため、スケジュール管理には注意が必要です。
複数年にわたって社員教育を進めたい場合は、年度単位で計画・申請を分けるとスムーズに進められます。
電気工事士の採用・定着を成功させるために、今すぐ始めるべきこと
電気工事士の資格取得を企業として支援することは、単なるスキルアップにとどまらず、「若手の採用強化」「定着率向上」といった経営課題の解決にもつながります。
なかでも、人材開発支援助成金のような制度を活用すれば、教育コストを抑えつつ、社内に継続的な研修の仕組みを築くことが可能です。ただし、制度には要件や申請タイミングなど注意点も多いため、「情報収集→設計→申請」の各段階を丁寧に進めることが重要です。
また、特に若手の電気工事士の採用・定着を目指すためには、ターゲットとなる“Z世代”の特性を理解しておくことも重要です。
そこで電気工事業界に特化した採用サイト・電工ナビでは、「若手が定着しない」「応募が集まらない」と感じている企業様におすすめの無料ダウンロード資料をご用意しています。
ぜひこちらもご一読ください。
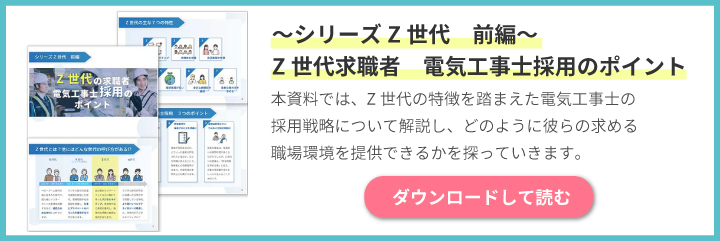
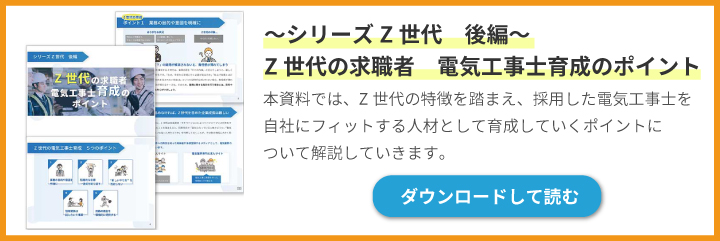
また、電工ナビのX(旧・Twitter)では、この記事のように電気工事業界の方に役立つ情報を日々発信しています。ぜひご登録ください。
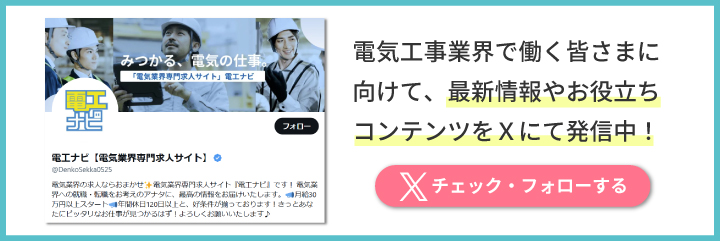
【情報提供元】
TEAM株式会社