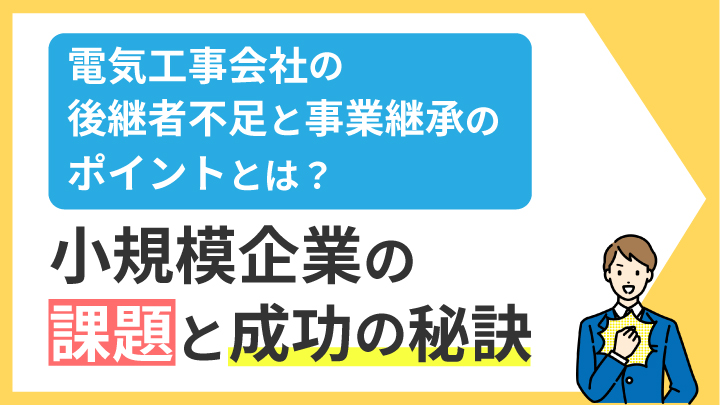2025.10.10
教えられる先輩がいない? 電気工事会社の教育体制をゼロから整える方法
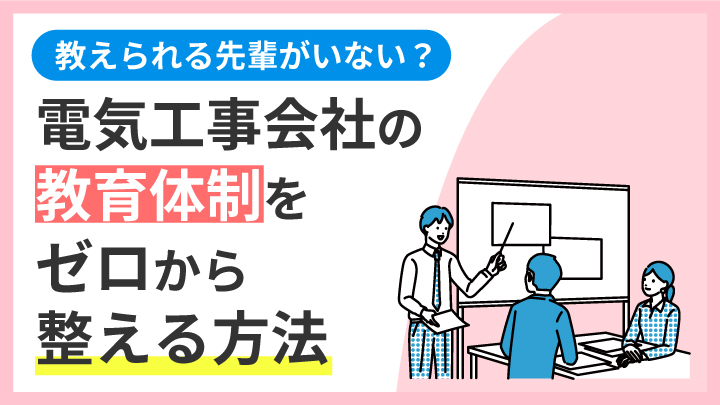
「若手社員が定着しない」 「ベテランが忙しくて新人を育てられない」
中小の電気工事会社を中心に、このようなお悩みを伺うケースが増えています。
「教育は現場に任せきり」「結局、本人のやる気次第」といった状況が続けば、育つはずの人材も辞めていき、現場の負担は増す一方です。
そこで本記事では、教育担当者に過度な負担をかけずに、育成を仕組みとして整える方法を解説します。
▼なお、若手不足や教育の属人化は、業界全体の構造的な問題でもあります。
こうした背景や定着課題については、「電気工事士の若手が定着しない理由とは?育成の壁とその乗り越え方」でも詳しく解説しています。
CONTENTS
電気工事会社で「教える人が足りない」根本原因とは?
電気工事業界では、多くの現場で「教えられる人の層が薄い」という課題が増えています。
これには単なる人手不足ではなく、教育を担える世代の高齢化や若手の入職減少といった構造的な要因があります。
若手不足と高齢化の実態
電気工事業界を含む建設業では、若手人材の減少と高齢化が同時に進行しています。この傾向は総務省の「労働力調査」など、各種の統計からも明らかです。
たとえば、令和5年の建設業全体の年齢構成を見ると、55歳以上が36.6%、29歳以下はわずか11.6%にとどまっています(※)。
この数字は、建設業の担い手の多くが中高年層に偏っていることを示しており、今後さらに“教える人”が不足するリスクがあります。
建設業のうち電気工事業に特化したデータは限られるものの、同様の傾向が強いと考えられます。特に中小企業では、現場を支えるベテラン層が高齢化する一方で、若手の採用が難航し、「教えたいけれど教えられない」状況に直面している企業も少なくありません。
(※)出典:総務省「労働力調査」
OJTに依存しすぎると起きる課題とは?
中小の電気工事会社では、「現場で先輩がつきながら教える」というOJT(On the Job Training)が主な教育手段となっているケースが多くあります。しかし、この方法にはいくつかの問題があります。
たとえば、教育内容が属人化しやすく、教える先輩によって内容や教え方にバラつきが出やすいこと。また、ベテラン社員が現場作業と教育の両方を担うことになり、時間的・精神的な負担が大きくなってしまう点も無視できません。
さらに、新人が失敗を繰り返すことで現場全体のストレスが増し、結果的に「誰も教えたくない」という雰囲気が生まれることもあります。
このように、OJTだけに頼った教育体制では、組織として人を育てる力が蓄積されにくく、継続的な人材育成が難しくなるというリスクをはらんでいます。属人化を防ぎ、再現性のある教育フローを整えることが、今後の人材確保の鍵を握ります。
仕組み化で新人教育を安定化させる3つのポイント
電気工事士の新人教育は、どうしても現場任せ・担当者任せになりがちです。しかし、教育を属人化したままでは、教える内容や質がバラつき、指導にかかる負担も大きくなってしまいます。
そこで必要なのが、「何を、誰が、どう教えるか」を可視化し、教育体制を“仕組み”として設計することです。
ここでは、現場負担を抑えつつ、新人教育を安定化させるための2つのポイントを紹介します。
ポイント1:スキルマップで「何を教えるか」を可視化
まずは、教えるべき内容を明確にするところから始めましょう。
電気工事の業務には、「配線作業」「器具取り付け」「安全確認」など、段階的に覚えるべき工程が数多く存在します。これらを一覧化し、「どの作業を、どのレベルまで習得すればよいか」を示したスキルマップを作成することで、教育の標準化が可能になります。
スキルマップとは、「従業員がどの業務を、どのレベルまで習得しているか」を一覧表で可視化したものです。電気工事の業務内容を細分化し、社員ごとの習熟度を段階的に記録します。
たとえば、以下のような形式です。
| 業務項目 | Aさん | Bさん | Cさん |
|---|---|---|---|
| コンセント取り付け | ◎ | △ | × |
| 配線工事 | ○ | ◎ | △ |
| 分電盤の結線 | × | △ | ○ |
| 図面の読解 | ◎ | ○ | △ |
◎:指導できるレベル ○:業務を自立して行えるレベル △:一部指導のもと実施可能 ×:未経験
スキルマップを活用することで、次のような効果が得られます。
・教育の抜け漏れや属人化を防げる
・指導者・被指導者双方の目標が明確になる
・習熟度の可視化により、評価
・処遇にも活用できる
作成する際には、次のような段階を踏んでいくと良いでしょう。
- 業務を細分化する(例:工具の名称理解、配線作業、図面読解、安全管理など)
- 習得レベルを定義する(例:未経験/補助可能/自立して実施/他者に指導可能)
- 従業員ごとに記入する
- 教育進捗に応じて定期的に更新する
スキルマップを作成することで、「教えるべきこと」「誰が教えられるか」「誰がどこまでできるか」を一目で把握できるようになるため、教育の設計と運用を一気に効率化できます。
ポイント2:教育担当のローテーションとチーム化
次に検討したいのが、「教える人を分散する仕組み」です。
新人教育を1人の先輩社員に任せきりにすると、教える側の負担が過大になり、育成の継続が難しくなるケースも見受けられます。これを防ぐためには、教育担当者をチーム制にすることが有効です。
教育担当のチーム化には次のようなメリットがあります。
・現場作業と教育の両立がしやすくなる
・複数人による視点で、指導の質が向上する
・教える側の精神的・物理的負担が軽減される
また、教育担当のローテーションを取り入れれば、全社員が「教える側」「育てる側」を経験する機会を得られ、職場全体の教育意識向上にもつながります。
ポイント3:マニュアルで教育のベースを共有する
教育体制づくりにおいて、スキルマップや教育担当のチーム化とあわせて検討したいのが「マニュアルの整備」です。
電気工事の現場では、先輩によって教え方が異なったり、「これは見て覚えるもの」という曖昧な伝達になりがちなケースも少なくありません。そうしたリスクを排除し、一定の指導レベルを保つための基盤としてマニュアルが役立ちます。
マニュアルといっても、業務すべてを文章化・網羅する必要はありません。むしろ、以下のような「使われる工夫」が重要です。
・写真
・図解を多用して、直感的に理解できる内容にする
・紙とデジタル(PDF・動画)を併用し、現場でも閲覧しやすくする
・内容は完璧を目指さず、現場の声を反映しながらアップデート可能にする
・スキルマップの項目に対応した解説を載せる
たとえば「コンセント取り付け」に関するマニュアルであれば、
・使用工具と注意点
・よくあるミスと対処法
・写真つきでの手順解説
・作業後の確認ポイント
といった実践的な内容が含まれていれば、新人にとっても、指導する側にとっても有用です。
また、指導時に同じ内容を複数回説明する手間を省けるため、教育負担の軽減にもつながります。
▼マニュアルの具体的な作り方や、現場で定着させるためのポイントについては、下記の記事で詳しく解説しています。
現場での成功事例から学ぶポイント
教育体制の整備に取り組んでいる中小電気工事会社では、属人化や負担の偏りといった課題をクリアしながら、成果につなげた事例が増えています。
ここでは、実際の現場で効果を上げた取り組みを紹介し、教育体制づくりのヒントを探ります。
階層別のステップ研修制度を構築した中小電気工事会社の事例
ある中小規模の電気工事会社では、これまでOJTに頼っていた新人教育を見直し、「階層別のステップ研修制度」を導入しました。
この制度では、社員を「未経験者」「若手職人」「中堅職人」「現場責任者」などに分類し、それぞれに必要なスキルや知識を明確化しています。
具体的には、次のような内容です。
・未経験者:工具の使い方、安全管理の基本
・若手職人:配線作業、図面の読み方
・中堅職人:工程管理、後輩指導の方法
・現場責任者:顧客対応、現場マネジメント
このように、段階的に習得していくスキルの内容を体系化した結果、「誰に何を教えるか」が明確になり、指導の負担が分散。加えて、本人にとってもキャリアの見通しが立ちやすくなり、定着率の改善にもつながっています。
助成金活用により教育コストを削減した事例
教育体制づくりにおいてネックになりやすいのが「コスト」です。そこで別の企業では、厚生労働省の「人材開発支援助成金」を活用し、電気工事士資格取得を支援しました。
たとえば第二種電気工事士の講習を受けさせたケースでは、以下のような支給がありました。
・講習費:36,000円(助成率60% → 21,600円支給)
・賃金助成:18時間 × 960円 = 17,280円 → 合計38,880円の助成を受けることに成功
このように、制度を活用すれば負担を抑えつつ社内育成に取り組むことが可能です。
▼人材開発支援助成金について詳しく知りたい方は、下記のコラムをお読みください。
教育体制づくりで失敗を避けるための注意点
教育制度を整備しようとする中で、「マニュアルを作ったのに定着しない」「教育担当が疲弊して制度が止まった」といった失敗例は少なくありません。
ここでは、実際の現場でよく起こるつまずきポイントを3つに整理し、実践的な注意点を解説します。
マニュアルだけでは教育制度は機能しない
ある企業では、教育マニュアルを一括作成したものの、「紙で配って終わり」「読んだかどうかの確認もなし」といった状態が続き、実際の現場では誰も参照していないという事態が起こりました。
このように、「マニュアル=仕組み」ではありません。作っただけで運用されていないマニュアルは、現場の負担になりこそすれ、育成にはつながりません。
重要なのは、「使われるマニュアル」に落とし込むことです。
・スキルマップと連動させて進捗をチェックする
・毎月のミーティングでマニュアルに沿って習得状況を確認する
・チームで指導内容を共有し、アップデートし続ける
このような運用ルールとセットで設計することで、マニュアルを社内に浸透させやすくなります。
教育担当の負担過多を防ぐ仕組みづくり
「若手に教えるのはいつも同じベテラン」という状況が続いた結果、教育担当者が過労気味になり、「もう教えたくない」と現場から離れてしまった――という声も聞かれます。
こうした失敗の原因のひとつに、個人の善意に頼った教育体制があります。この状況を改善するためには、教育担当をチームで担う「分散・共有型の仕組み」が必要です。
・担当者を固定せず、ローテーションで支援し合う
・教える内容を分担し、全員が“教える経験”を積む
・定期的に教え方や指導ポイントを共有する機会を設ける
ベテランに限らず、「少し前まで新人だった若手」が“教える側”に立つことで、負担軽減だけでなく、若手社員自身の成長機会にもつながります。
継続可能な研修を構築するための設計ポイント
「年度初めに盛り上がってスタートした教育制度が、半年後には誰もフォローしなくなっていた」という失敗例は多くの企業で見られます。
このように、教育制度が続かない最大の要因は、完璧を目指しすぎて現場に定着しないことです。
継続性を高めるためには、以下のようなポイントを押さえた設計が不可欠です。
・最初から完璧を目指さず、段階的に導入
・改善する
・年間スケジュールに研修タイミングを組み込む
・社内で評価や報告の仕組みを取り入れる
・自社に合った“最小限の型”から始める
制度を無理に回そうとするのではなく、現場の声を聞きながら柔軟にアップデートできる体制こそが、長く機能する教育制度の土台となります。
電気工事会社の教育体制づくりでよくある質問
ここでは、新人教育や社内制度の整備に取り組む中で、多くの中小電気工事会社が抱える疑問をQ&A形式でまとめています。
教育制度を整えるにはどれくらいのコストが必要?
必要なコストは、制度の内容や導入規模によって異なりますが、初期段階では大きな設備投資をせずに始めることも可能です。
・スキルマップはExcelやスプレッドシートで自作可能
・マニュアル作成は現場の作業手順を写真や動画で記録するだけでも効果的
・外部研修の活用や助成金(人材開発支援助成金など)を使えばコストを抑えられる
など、スモールスタートしてから改善を重ねるスタイルが現実的です。
ベテランがいない会社でもOJTは成立する?
A. ベテラン社員が少ない場合でも、OJT(On-the-Job Training)は工夫次第で成立可能です。
・若手社員が「自分より1~2年先輩」に教わるスタイル
・外部の講師や動画教材を併用するハイブリッド型
・チーム全体で教える「ペア指導制」
近年では、このような指導者のレベルに依存しないOJTの方法が注目されています。
教えること自体が若手社員の成長にもつながるため、“教える文化”を社内に育てるという意識が大切です。
教育担当にする人がいない場合、どう育成担当を起用する?
人手が足りない状況では、「育成担当を専任で配置する」のは難しいかもしれません。そこでおすすめなのが、“兼任+チーム制”の起用方法です。
・現場リーダーや若手の中から「教えることに関心がある人」を育成係に任命
・指導担当を業務ごとに分けて役割分担(例:安全管理/工具の使い方など)
・定期的に「教え方」のミーティングを行い、互いに支え合う体制を作る
といった方法により、少人数でも教育体制を分担・継続できる仕組みが構築できます。
現場任せから脱却し、育てる会社への一歩を踏み出すために
電気工事士の育成を仕組み化するには、まず「何を教えるか」を見える化することが大切です。
たとえばスキルマップの作成だけでも、教育の軸が定まり、担当者の負担軽減にもつながります。
あわせて、人材開発支援助成金を活用すれば、コストを抑えて教育体制を整えることが可能です。評価や支援が当たり前になる文化を築き、若手が育つ職場を目指しましょう。
電気業界に特化した求人サイト「電工ナビ」では、採用後の育成や定着支援まで見据えた情報を発信中です。
Z世代を惹きつける育成法や、教育制度の整え方に悩んでいる方は、ぜひ下記の無料資料やSNSもご活用ください。
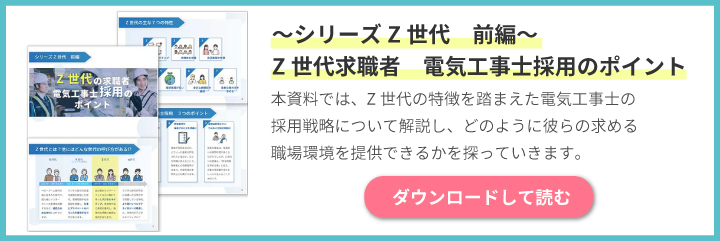
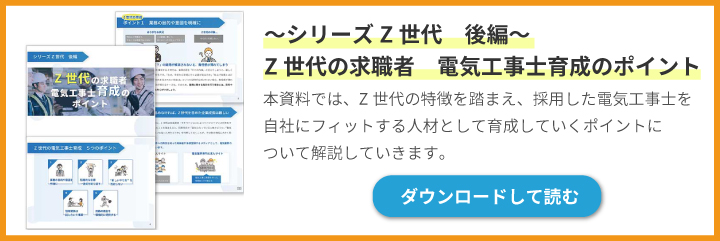
また、電工ナビのX(旧・Twitter)では、この記事のように電気工事業界の方に役立つ情報を日々発信しています。ぜひご登録ください。
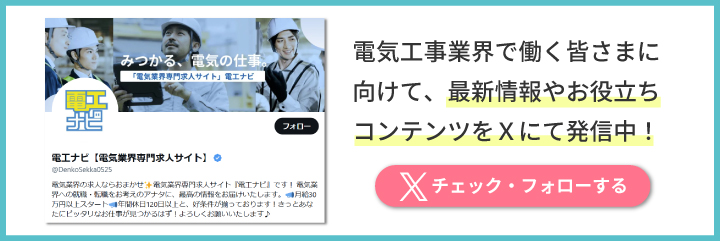
【情報提供元】
TEAM株式会社