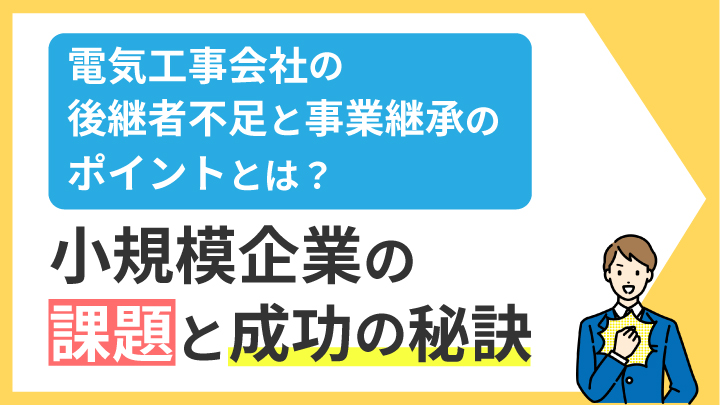2025.08.29
離職理由から見る!電気工事士の定着率を上げる具体策とは?
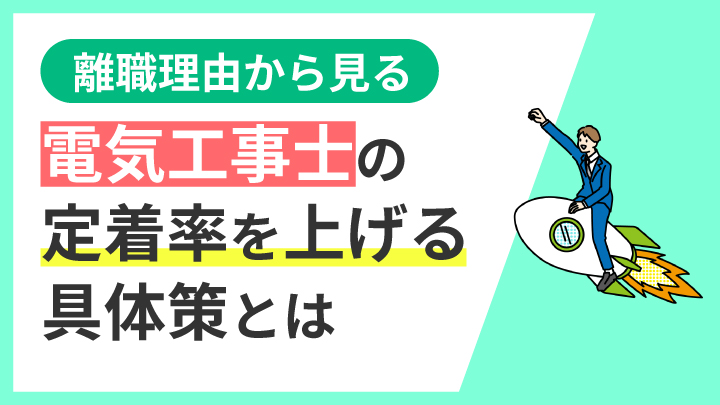
電気工事士の定着率に課題を感じている企業は少なくありません。
せっかく採用しても、数ヶ月で辞めてしまう…その背景には、業界特有の「離職理由」が存在しています。
本記事では、実際に多く見られる離職の原因を解説した上で、定着率を向上させるための具体策を紹介します。特に小規模事業者でも実践できる工夫にフォーカスし、採用から定着まで一貫して改善するヒントをお届けします。
CONTENTS
なぜ電気工事士は離職しやすいのか?
電気工事士は社会インフラを支える重要な専門職であり、常に需要が高い一方で、定着率の低さに悩む企業が少なくありません。
「若手が定着しない」「すぐ辞めてしまう」といった課題の裏には、いくつかの共通した原因が存在します。
ここでは、電気工事士の平均離職率と、特に多い3つの離職理由について整理し、定着率を高めるための前提理解を深めていきます。
電気工事士の平均離職率とは?
経済産業省の資料(※)によると、電気工事業界の3年後離職率は20~40%で、他産業に比べてやや高い傾向にあります。
電工ナビでも、特に20代前半の若年層や未経験から入社した人材の離職についてのお悩みを企業の採用担当者から聞く機会が多く、「半年以内に辞めてしまう」といった事例も現場では珍しくありません。
人材の採用にかかるコストや手間を考えれば、「長く働いてもらうこと」は事業継続にとっても非常に重要なテーマです。
主な離職理由①:体力的な負担と労働環境
電気工事の現場では、高所作業・屋外作業など、体力を必要とする業務も多く発生します。
特に夏場や雨天時の作業は負担が大きく、未経験入社の若手にとっては想像以上のハードさとなることも。
また、繁忙期の長時間労働や、休みの取りづらさが続くと、「この働き方をずっと続けるのは無理かもしれない」と感じてしまうも少なくありません。
主な離職理由②:人間関係と現場の指導体制
中小企業の電気工事会社では、職場内の人間関係や指導方法に起因する離職が目立ちます。
たとえば、
- ・質問しづらい雰囲気
- ・経験豊富な職人による感覚的な指導
- ・言葉遣いが荒く、威圧的に感じられる
といった環境があると、特に若手は「馴染めない」「ついていけない」と感じ、離職を選択しやすくなります。
主な離職理由③:キャリア・将来像の不透明さ
資格取得や昇格の流れ、将来の働き方について、会社として明確なビジョンを示せていないことも離職の一因です。
「頑張っても評価されない」「いつまでこの働き方が続くのか分からない」といった不安が募ると、他社や他業種への転職を考えるきっかけになります。
特に20代の若手にとっては、「この仕事を続けた先にどんな未来があるのか?」という納得感が、定着の鍵を握っています。
▼若手の離職を防ぐには、個別の対策だけでなく「評価」「成長支援」「職場環境」をどう設計するかという全体像を押さえることも重要です。定着の考え方を体系的に整理した下記の記事も参考にしてみてください。
電気工事士の定着率を上げるには何をすべきか?
電気工事士の定着率を高めるためには、「辞める理由」を減らすと同時に、「働き続けたい」と思える要素を増やす必要があります。
実際に電工ナビに掲載する企業の中でも、応募者から選ばれやすい会社や、入社後の定着率が高い会社には共通点があります。ここでは、主な4つの改善ポイントについて解説していきます。
改善策①:職場環境の見直し
電気工事士の離職理由として多いのが、「長時間労働」や「体力的なきつさ」といった職場環境の問題です。
ただし、現場の環境は元請け都合で決まるため、会社側で整備できる部分は限られます。
だからこそ、直行直帰の許可や、作業量の平準化による残業削減、有休取得の促進など、自社でコントロールできる点を見直すことで、社員の負担軽減につながります。熱中症対策や防寒具支給などの安全面への配慮も、定着率を左右する重要な要素です。
改善策②:教育体制の強化
「現場で見て覚えろ」「誰も教えてくれない」といった声は、電気工事業界で目立つ離職理由のひとつです。とくに未経験者にとって、業務内容や用語すらわからない状態で業務を任されるのは、不安が積み重なりやすくなります。
そこで効果的なのが、OJT(オン・ザ・ジョブトレーニング)の導入です。ベテラン社員が一定期間ついて指導する体制を整えることで、技術だけでなく、精神面のフォローも可能になります。加えて、「メンター制度」のように、相談しやすい先輩をつけると、技術以外の悩みも気軽に話せるようになります。
こうした工夫により、小さな疑問やつまずきを早期に解消することが、モチベーション維持と早期離職の防止につながります。
▼未経験者の不安を減らすには、「誰が教えても同じ基準で学べる仕組み」を用意することが欠かせません。現場教育を属人化させないための具体的なマニュアル整備については、こちらで詳しく解説しています。
改善策③:将来のキャリア提示とモチベーション設計
目の前の仕事だけでなく、「この仕事を続けると、次にどんなステップがあるのか」をあらかじめ伝えておくことで、安心感とやる気が生まれます。
たとえば、「電気工事士2種 → 電気工事士1種 → 施工管理技士 → 職長」というような成長の流れを説明しておくことで、働く人のモチベーションを高めることができます。
改善策④:採用時のミスマッチを防ぐ情報開示
「入社してみたら、聞いていた話が違った」というギャップは、早期離職の最大の原因です。
特に中小企業の場合、求人票だけでは雰囲気や実態が伝わりにくいため、求人原稿や面接でいかに職場のイメージを持たせられるかが鍵を握ります。
具体的には、
- ・現場写真や社員インタビューの掲載
- ・実際の一日の流れ
- ・労働時間や休日日数の実績データ
など、働く姿をリアルに伝える工夫が必要です。また、面接時には「合うかどうか」をお互いに確認できるよう、企業側からの質問だけでなく、双方向の対話も意識すべきです。
他社はどうしている? 電気工事会社の成功事例
ここでは実際の定着率改善の取り組みを参考に、成果につながったポイントを紹介します。
成功事例①地場企業の3年定着率向上策
地元で30年以上続く小規模な電気工事会社では、3年以内の離職率が以前は50%近くに達していました。
しかし、入社後の1ヶ月間に「習熟度チェックリスト」を活用した進捗確認を行うようにしたところ、早期離職が大幅に減少。職長が定期的に面談を行い、不安や疑問をこまめに解消する取り組みも定着率向上につながっています。
成功事例② 面接時の「条件説明書」でミスマッチ回避
別の会社では、「求人票に書いてある内容と違った」と言われることが多く、応募数のわりに定着しない課題がありました。
そこで、面接時に「勤務時間·休日·給与などの条件をまとめたA4用紙」を手渡す運用を開始。結果として、「話が違う」と感じる応募者が減り、入社後のトラブルも大きく減少しました。
成功事例③ 若手の声を取り入れた改善施策
ある若手社員が「現場に何を持っていけばいいかわからず不安だった」と話したことをきっかけに、「新人マニュアル」と「持ち物リスト」を作成した会社もあります。
社内ミーティングで若手社員の声を拾い、改善につなげたことで、未経験者の不安が軽減され、働きやすい職場づくりにもつながりました。
電気工事士の定着率向上でよくある質問
電気工事業界の離職率はどれくらい?
経済産業省の資料によると、電気工事業界の3年後離職率は20~40%で、他産業に比べてやや高い傾向にあります。
特に初年度の離職が多くなりやすいため、入社前に業務内容や職場環境のリアルを丁寧に伝えるなど、ミスマッチによる早期離職を防ぐ取り組みが重要です。
【出典】経済産業省「電気保安人材の中長期的な確保に向けた課題と対応の方向性について」
採用面接で伝えるべき内容は?
仕事内容・労働時間・給与・休日などの条件だけでなく、「何に困りやすいか」「どうサポートするか」を伝えることが大切です。
特に未経験者には、教育体制や先輩社員のフォロー体制を具体的に説明しましょう。
入社後の人間関係のトラブルを防ぐための対策は?
人間関係のストレスは離職の大きな要因です。
現場リーダーとの相性や、指導スタイルのすり合わせを面接段階で行うほか、入社初期に定期面談を設ける仕組みがあると、心理的な不安が減りやすくなります。
定着率改善は「採用後の仕組みづくり」と「ミスマッチの回避」から
ここまで解説したように、電気工事士の離職理由には、労働環境や人間関係、キャリアの不透明さなど、さまざまな要因があります。こうした問題に対応するには、働きやすい職場づくりや教育体制の整備など、採用後の仕組みづくりが欠かせません。
しかし、もうひとつ見落とせないのが「採用の時点で起こるミスマッチ」です。
仕事内容や労働条件、現場の雰囲気などが、求職者の想定と大きくズレていた場合、どれだけ職場環境を整えても、早期離職につながるリスクは避けられません。
だからこそ、「現場の実情を正しく伝えられる求人原稿」と、「業界に理解のある求職者との接点」を持つことが、定着率向上の第一歩です。
定着につながる採用を、電工ナビではじめよう
電工ナビは、電気工事業界に特化した求人メディアとして、以下のような特長を備えています。
- ・掲載費用0円
- ・成果報酬型で、気軽に始められる
- ・電気業界に関心のある求職者が多数登録。経験者比率も50%超
- ・求人検索エンジンと自動連携で、露出力が高い
- ・全額返金保証つきで、早期離職のリスクにも備えられる
また、職場環境や仕事内容を正しく・わかりやすく伝える求人原稿を作成代行するプランもご用意しています。
「求人原稿をただ掲載するだけ」ではなく、「定着まで見据えた採用」を実現しませんか?
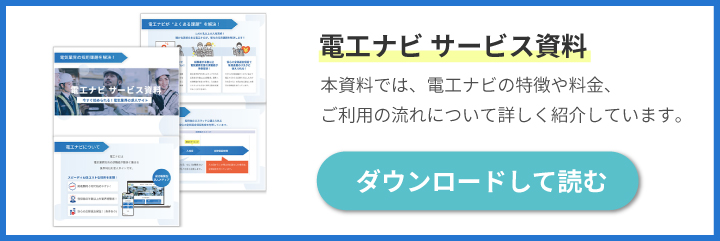
Z世代採用なら、こちらもチェック
電工ナビでは「若手が定着しない」「応募が集まらない」と感じている企業様におすすめの無料ダウンロード資料をご用意しています。
ぜひこちらもご一読ください。
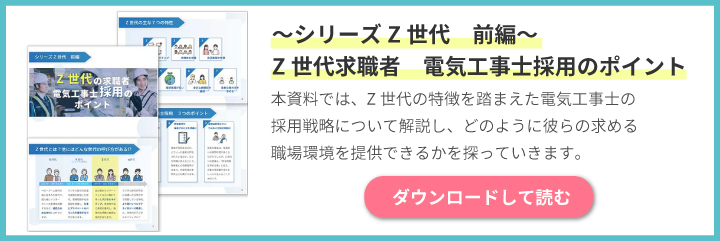
【情報提供元】
TEAM株式会社