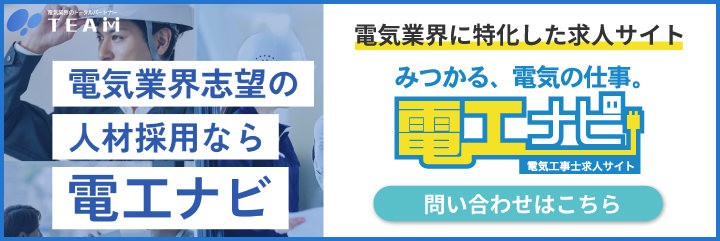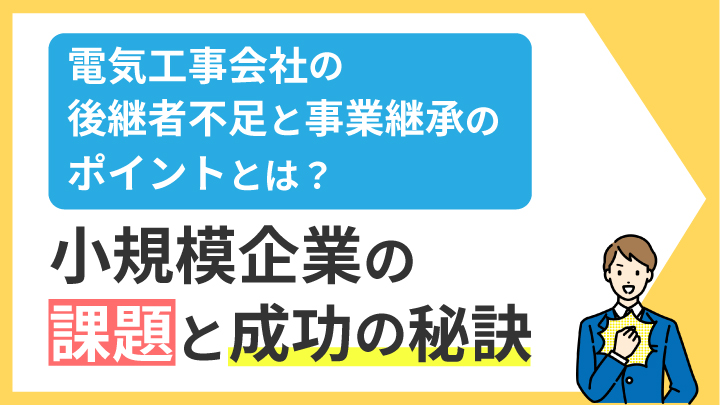2025.08.29
電気業界の求人広告費は高い? 費用対効果を見える化し、改善につなげる方法
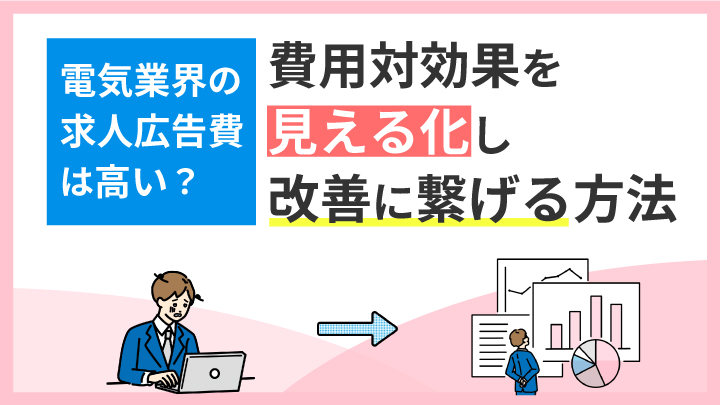
「求人広告を出しても応募が少ない」 「コストばかりかかって採用できない」
電気工事会社の採用担当者の方から、このような求人広告費に関するお悩みを聞く機会が増えてきました。
求人広告費は業種や媒体によって相場が異なるうえ、費用対効果が見えにくいのが実情です。
本記事では、電気業界における求人広告の費用相場や、費用対効果の見える化の手法、そして改善のための考え方と具体策をわかりやすく解説します。
求人媒体を選ぶ前に、「そもそも電気業界でなぜここまで人材不足が深刻化しているのか」を把握しておくと、採用戦略の精度が大きく高まります。業界の背景から整理したい方は、こちらのコラムもご覧ください。
CONTENTS
電気業界における求人広告費の相場とは?
電気工事士を採用しようと求人広告を出す際、「どのくらいの金額が目安なのか」と不安になる方は多いのではないでしょうか。
実際、求人広告費は媒体の種類や掲載期間、地域、職種の専門性によって大きく変動します。
特に電気工事士のように資格が必要で、かつ人材不足が続く業界では、採用単価が高騰しやすい傾向にあります。ここでは、電気業界における求人広告費の目安と、使用される媒体の傾向について解説します。
掲載課金型・成果報酬型の違いと相場
求人広告には、主に以下の2つの料金体系があります。
| 掲載課金型(定額制) |
求人情報を●週間●円という形で掲載するタイプです。 中途採用では、1案件あたり20万円~100万円程度の掲載費が相場とされます。媒体によっては、1週間単位で契約できるものもあります。 |
| 成果報酬型(成功報酬制) |
採用が決まった段階で料金が発生するモデルです。 1人採用するごとに、100万円~200万円前後が相場とされ、若手や資格保持者の採用では高額になるケースもあります。 |
採用人数が限られている小規模企業の場合、「成果報酬型」は初期費用がかからない点でメリットがあります。
しかし、1件あたりの単価は「掲載課金型」と比べて高いため、「5~10名を一気に採用したい」といった場合は割高になる可能性があります。
逆に「掲載課金型」は、企業のブランド力やタイミング、原稿設計によって反応が大きく変わるため、広告の運用力が問われます。
採用で成功する企業が支払っている求人広告費の目安とは
前述の通り、選定する媒体によって相場が異なるため、一概に目安を出すことは難しいです。
ただ、電気業界特化の求人サイト「電工ナビ」における採用実績を踏まえると、採用に成功している企業では、採用1人あたり20万円~30万円程度の求人広告費をかけています。
電気工事業界に多い掲載媒体の傾向
電工ナビの知見を踏まえると、電気工事士の求人広告で成功するためには次のような要素を押さえておくことが重要です。
・専門性の高い媒体の選定が有利に働きやすい
業界に特化した求人サイトや、職人系求人に強い媒体は、応募者のマッチ度が高く定着にもつながりやすい傾向があります。
・クリック課金型の求人媒体を活用すると応募率が高まりやすい
地方や小規模事業者では、Indeedをはじめとする、無料でも掲載できるクリック課金型(CPC)の求人検索エンジンがよく使われています。
こうした媒体は集客に強みがあるため、他の求人サイトと併用することで応募率が高まりやすいです。
・自社採用ページと連動した施策で信頼性を向上
最近では、求人媒体だけに頼らず、自社の採用ページと連動した運用(オウンドメディア型採用)を行うケースも増えています。
この場合、企業理解を深めた上での応募が期待でき、採用の費用対効果が改善しやすくなります。
求人広告の費用対効果とは?どうやって見える化する?
求人広告費という採用への投資がどれだけ成果につながっているか、どう判断すればいいのでしょうか?
ここからは、採用単価の計算方法をはじめ、応募·面接·採用の歩留まり分析や、見えにくい内部コストの算出方法について詳しく解説します。
「採用単価」の計算方法(求人広告費 ÷ 採用人数)
求人広告の費用対効果を語るうえで、最も基本となるのが「採用単価」という指標です。これは以下の式で求めることができます。
採用単価=(求人広告費+成果報酬+運用コスト)÷採用人数
たとえば、月額50万円の求人サイトに3ヶ月掲載した場合、求人広告費は150万円となります。この広告で2名を採用できた場合の採用単価は75万円です。
一方、1人あたり30万円の成果報酬型のサービスを利用した場合、掲載費は無料で、採用単価はそのまま30万円となります。
どちらの方式であっても、採用単価という共通指標で「数字を見える化」することで、自社の費用対効果を客観的に評価することができます。
応募数・面接率・採用率からみる効果指標
採用単価だけでは、求人広告のどの部分に課題があるかまでは見えません。
採用がうまくいかない場合、「どの段階でつまずいているのか」を知るための歩留まり指標も重要です。以下のような数値を定期的に把握することで、改善のヒントが得られます。
| 応募率 | 広告閲覧数に対する応募数の割合 | 求人原稿の魅力・訴求力を確認 |
| 面接率 | 応募数に対する面接実施の割合 | 応募者対応の速さや質を確認 |
| 採用率 | 面接数に対する採用率の割合 | 面接の質・条件の魅力を確認 |
たとえば、成果報酬型で応募数はあるが面接に至らない場合、「応募の質が合っていない」「レスポンスが遅い」といった原因がある可能性があります。
逆に、掲載課金型で閲覧数が多くても応募がない場合は、「原稿の内容が弱い」「条件が魅力的でない」などの課題が考えられます。
媒体の種類にかかわらず、歩留まりを数値で可視化することで、改善の打ち手が明確になります。
内部コスト(工数・稼働)も含めて考える
費用対効果を判断するうえで見落とされがちなのが、「内部コスト」です。
求人媒体への支払いだけでなく、以下のような社内でかかっている人件費や時間コストも含めて考えましょう。
具体的には、次のようなコストです。
・掲載媒体の選定や原稿作成にかかった時間
・応募者とのやり取り(メール返信·電話調整など)にかかる人件費
・面接·教育·入社フォローに関わった現場の時間コスト
たとえば、原稿作成に慣れておらず時間がかかりすぎる場合には、媒体側が用意している原稿作成サービスなどを利用することで、結果としてコストを削減することができます。
表面的な金額だけで比較せず、トータルのコスト(外部+内部)で判断することが、真の費用対効果を見極めるポイントと言えるでしょう。
求人広告の効果が出ない理由と改善策
「求人広告を出しても応募が来ない」
「応募はあるものの、面接や採用につながらない」
このような場合、「求人媒体が悪いのでは?」と考えがちですが、実は広告の中身や運用方法に課題があるケースも少なくありません。
ここでは、電気工事業界の求人広告でよくある失敗パターンや、見落としがちな改善ポイントについて解説します。広告費を無駄にしないためにも、「出して終わり」ではなく、継続的な改善視点を持つことが重要です。
求人広告の出稿でよくある失敗パターン
まずは、求人広告でよく見られる失敗例を紹介します。
失敗パターン1:原稿と実際のミスマッチ
・実際より良く見せようとする表現が多く、入社後にギャップが生まれる
・仕事内容や勤務時間、給与条件が曖昧で、求職者が不安を感じる
このような場合、応募数が増えたとしても面接辞退や早期離職につながるおそれがあります。
失敗パターン2:読みづらい・伝わらない原稿構成
・長すぎる文章で要点がつかみにくい
・写真やレイアウトがなく、企業の雰囲気が伝わらない
これでは、求職者に求人の詳細を読んでもらう前に、離脱されてしまいます。
失敗パターン3:応募者対応が属人化していて対応品質がばらつく
・応募メールを社長や現場リーダーが個別に確認しており、対応タイミングが不規則
・面接設定や条件確認がその場しのぎの対応になりやすく、候補者への伝え方が毎回違う
・窓口が明確でなく、連絡ミスや返信漏れが起きやすい
こうした対応は求職者側に「この会社は対応が曖昧」「ちゃんと管理されていない」という印象を与えてしまい、面接辞退や選考離脱を招いてしまいます。
応募前の「離脱」ポイントを分析する視点が重要
求職者の立場から見ると、求人広告に「興味を持つ」→「詳細を見る」→「応募する」までにはいくつものステップがあります。
その中で、どこかのタイミングで離脱している可能性を常に意識しましょう。
検索されているがクリックされない場合
タイトルや画像・原稿に魅力がなく、離脱されている可能性が高いです。働く人の声や現場写真など、リアリティのある情報を掲載して読み手の関心を惹きつけましょう。
求人の詳細ページまで来ているが応募されない場合
給与や福利厚生など、条件面で競合他社に流出しているおそれがあります。最近では、給与だけでなく働きやすさなども求職者が企業を選定する重要なポイントです。自社で提示できる条件について、改めて検討してみましょう。
応募後に面接につながらない
初期対応が遅いと競合他社に流出してしまう可能性が高まります。応募があったらできるだけ当日中に連絡を取る体制を整えるなどの工夫が重要です。
このように、求人広告の効果が出ないと感じたときは、媒体の選定だけでなく「原稿内容」「応募導線」「対応体制」といった運用全体”の見直しが必要です。
特に中小企業の場合、「応募があったのに面接につながらなかった」「離脱ポイントを把握していなかった」ことで、本来採用できたはずの人材を逃してしまっているケースが少なくありません。
効果が出ない原因を分解し、1つずつ見直していく姿勢が、費用対効果の改善につながります。
【事例】求人広告の改善と費用対効果の向上
ここでは、ある中小規模の電気工事会社が行った求人広告改善の取り組みをご紹介します。
課題:求人広告費だけが膨らみ、応募ゼロの状態
この会社では、複数の求人媒体に半年間で60万円以上をかけていたものの、応募はごく少数で、採用にはまったくつながらない状況が続いていました。
媒体は汎用的な求人検索サイトで、出稿のタイミングや内容は担当者任せの状態。
社長は「求人広告を出せば応募は来る」と考えていたものの、実際には原稿はテンプレートのままで、仕事内容や魅力、職場の雰囲気が十分に伝わっていませんでした。
さらに、応募対応も現場の合間での対応となり、返信が遅れたり、対応がぶっきらぼうになってしまったりすることもあり、応募者からの印象も良くなかったといいます。
改善の取り組み:求人原稿の改善+導線整備で応募3倍
こうして同社では、主に2つの改善策に取り組みました。
改善策1:業界特化型の媒体へ切り替え
大手媒体では応募がこなかったため、電気工事業界に特化した求人媒体に変更。
職種や資格に理解のある求職者層に情報が届きやすくなったことで、初回掲載から実務経験者の応募を複数獲得できました。
改善策2:求人原稿と応募対応体制の見直し
・仕事内容、1日の流れ、求める人物像などを具体的に記載し、職場のリアルを伝える構成に変更
・原稿に写真やインタビューを追加し、「ここなら馴染めそう」と感じられる印象づくり
・応募には事務スタッフが一次対応し、24時間以内の返信体制を確立
このような見直しの結果、掲載初月の応募数は従来比3倍以上に増加。2名の採用に成功し、採用単価もこれまでの約半分の水準(30万円台)に抑えることができました。
改善が生んだ「定着率」への波及効果
こうした改善の取り組みは、別の波及効果も生んでいます。
まず、業界特化の媒体に切り替えたことで「業界理解のある求職者」からの応募が増えました。また、原稿改善によって入社前の情報ギャップが減ったことで、早期離職ゼロという結果にもつながっています。
さらに、応募対応を分担しフローを整えたことで、社長が本来の業務に集中できる体制も構築することができました。
「採用活動=負担」という印象が、「採れる・続く・回る仕組み」として社内に定着しつつある好事例と言えるでしょう。
電気業界の求人広告費改善でよくある質問
求人広告にどのくらい費用をかけるべきですか?
一般的に、電気工事士の採用1名あたりにかける広告費は20万~100万円が目安です。
ただし、地域や職種の専門性、媒体によって大きく変動します。
自社の採用目標や過去の採用実績をもとに、費用対効果を意識して設定することが重要です。
成果報酬型と掲載課金型、どちらが向いていますか?
採用人数が限られている場合や初期費用を抑えたい企業には成果報酬型が適しています。
一方で、複数名を同時に採用したい場合は掲載課金型が有効です。両者の特性を踏まえ、状況に応じた使い分けが重要です。
掲載費をかけずに採用する方法はありますか?
掲載費ゼロでスタートできる成果報酬型の求人媒体を活用するのが一つの方法です。
たとえば「電工ナビ」では、電気業界に特化した求職者に直接アプローチでき、応募から採用までのサポートも充実しています。無駄なコストをかけずに、効率よく採用したい企業におすすめです。
掲載費ゼロで、電気業界経験者に直接アプローチ
ここまで、電気工事業界における求人広告費の考え方と、改善のポイントについて詳しく解説してきました。
ただ、一度に改善策を全て実施するのは簡単ではありません。そんな時こそ、業界特化×成功報酬型の「電工ナビ」を試してみませんか?
電工ナビは、次のような特長を持つ求人サイトです。
・掲載費ゼロ·期間無制限で始めやすい
・経験者·電気業界志望者が多数登録
・indeedや求人ボックスなどの求人検索エンジンと自動連携
・万が一の早期退職にも全額返金保証つき
費用対効果に悩む電気工事会社の多くが、コストを抑えて理想の人材に出会っています。
掲載については、下記よりお気軽にご相談ください。
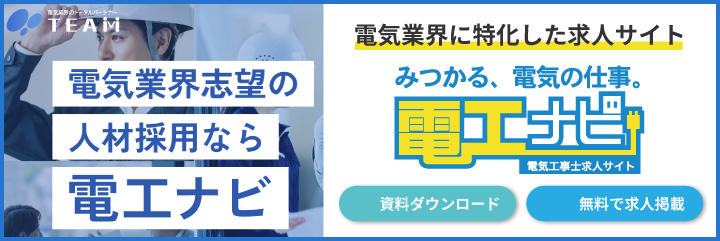
また、電工ナビでは求人メディア選定でお悩みの方に向け、5分でお読みいただける無料の資料をご用意しております。ぜひこちらもご一読ください。

・『電気工事士採用のための求人メディア選定 3つのポイント』
【情報提供元】