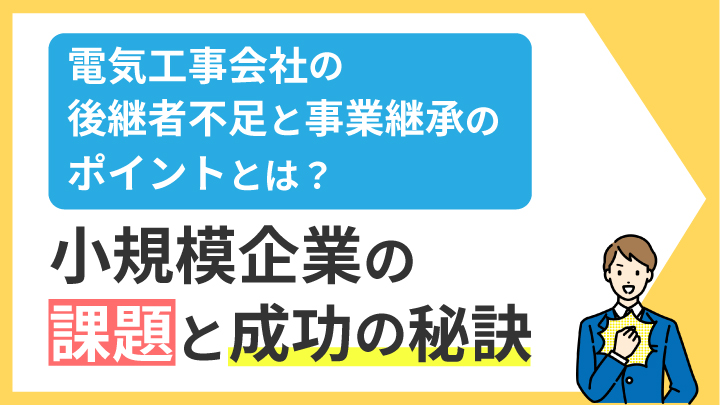2025.08.01
一人親方として独立するには?電気工事士の開業準備と注意点まとめ
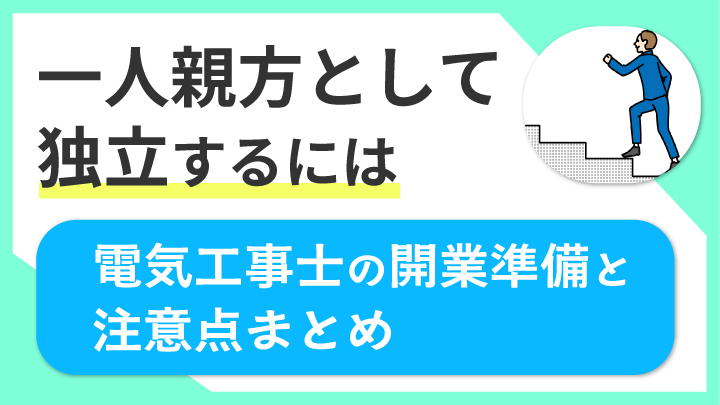
「独立したいけれど、どれくらい資金が必要か、どのような手続きが必要か、わからない」
「独立後に仕事を安定して受けられるか、心配…」
電気業界で一人親方を目指すにあたり、このようなお悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、電気工事士として独立し、“一人親方”という自由な働き方を実現したい方、将来的に“経営者”として会社を育てたい方へ向け、独立前に押さえておくべき準備・資金計画・メリット/デメリット、そして独立後に安定して受注を得るコツをわかりやすく解説します。
CONTENTS
なぜ今、電気工事士として“独立”を目指す人が増えているのか
慢性的な人手不足が続く電気工事業界では、再エネ設備やスマート住宅など新技術に対応するための案件が年々増加しています。
こうした中、「新規の依頼はあるものの、人手不足で受注できない…」という課題を抱える電気工事会社がいる一方で、その状況を高収入やキャリアアップを狙えるチャンスと捉え、独立に踏み切る電気工事士が少なくありません。
また、一人親方を目指す方の中には、勤務時間や案件を自分で選べる“自由な働き方”を求める声も多く、そうした想いも独立の決断を後押ししています。
職人としての経験を活かせる“自由な働き方”
電気工事士が独立するメリットとして、案件の選定や工期・工程をある程度コントロールできる点があります。これにより、会社勤めでは得にくい“より自由な働き方”を手にできます。
もちろん、独立前の実績や技術力は不可欠ですが、それらが評価されれば元請や顧客からの信頼を得やすく、リピーターや紹介が増えて大幅な収入アップも期待できます。
さらに、現場ごとに異なるニーズへ柔軟に対応し、品質とスピードを両立できれば、口コミ評価が高まるなど、やりがいを実感しやすい点も魅力です。将来的に法人化することができれば、職人から経営者へのキャリアアップの道も開くことができます。
一人親方として実績を積んだ先には、法人化という選択肢もあります。
「いつ・どの段階で会社にすべきか」については、以下で詳しく整理しています。
独立を考えたとき、まず何をすべきか
独立を検討する場合、いきなり行動に移せる人は多くないでしょう。まずは全体像を把握し、手続きや資金計画など「やるべき順番」を整理することが大切です。
ここでは、独立・開業に向けた流れをステップ別に解説していきます。
ステップ1:独立の意思決定
独立は人生の大きな転換期であり、綿密な計画と準備が必要です。税理士・社労士・中小企業診断士、金融機関の融資窓口、そして既に独立している先輩などに相談し、不安や疑問を解消しながら具体的な計画を固めましょう。
十分な情報を集めてリスクとメリットを比較検討し、最終的な意思決定へつなげることが大切です。
ステップ2:資格・登録要件の確認
独立を目指す電気工事士が登録手続きを行うには、第二種または第一種電気工事士の資格が必須です。登録手続きは施工内容や建設業許可の有無により、以下の4区分に分かれます。
|
名称 |
概要 |
|
登録電気工事業者 |
建設業許可がなく、一般用・自家用電気工作物の工事を行う場合に必要な基本登録 |
|
みなし登録電気工事業者 |
電気工事業の建設業許可を取得している事業者が、登録に準じて扱われる区分 |
|
通知電気工事業者 |
軽微な電気工事のみを行う場合に、都道府県へ簡易な通知を行う区分 |
|
みなし通知電気工事業者 |
建設業許可があり、軽微工事のみを行う場合に適用される簡易通知扱い |
ステップ3:事務所・車両・工具の準備
事務所(自宅兼用可)の確保、作業車両の選定・リース見積、電動工具や安全備品の購入リストをまとめて整理し、漏れなく手配することが大切です。
ステップ4:税務署へ開業届を提出
電気工事業として独立する際は、個人事業の開業届を所轄の税務署に提出しなければなりません。提出から受理までは通常1〜2週間かかるため、スケジュールに余裕を持ちましょう。
ステップ5:都道府県へ登録電気工事業者の届け出
電気工事を請け負うには、営業エリアの都道府県に「登録電気工事業者届出書」を提出し、営業所・主任技術者などを登録する必要があります。
|
分類 |
主な要件・書類 |
補足 |
|
資格 |
第二種 または 第一種電気工事士 |
工事内容により第一種が必要になる場合あり |
|
実務経験 |
目安:3年以上 |
実務経歴証明書で証明。自治体によって年数基準が異なることも |
|
保険加入 |
損害賠償責任保険・労災保険など |
加入証明書を添付し、工事リスクに備える |
|
事業主体情報 |
登記簿謄本(法人) / 住民票(個人)など |
事業者の身元を示す書類 |
申請書式は各都道府県のホームページからダウンロードできます。
例:東京都の場合は東京都産業労働局 電気工事業者登録ページ
書式や手数料は自治体ごとに異なるケースがあります。提出前に各都道府県の公式サイトや窓口で最新フォーマットを確認し、添付漏れがないか点検することが大切です。
ステップ6:営業ツールの整備
受注に向けて、顧客対応のための準備を進めましょう。最低限、名刺は必要ですが、余裕があればオンライン・オフライン双方で顧客接点を広げるため、WebサイトやSNSのアカウントを開設することが効果的です。
|
優先度 |
ツール |
目的 |
|
高 |
名刺 |
現場や打ち合わせで即座に渡せる基本ツール。会社名・連絡先・対応可能工事を明記 |
|
中 |
Webサイト |
会社概要や施工実績を掲載し、信頼性を高める営業ハブとして機能 |
|
低 |
SNS・Googleマップ |
SNSで情報発信し、Googleマップに事業登録して検索時の露出を補完 |
必要に応じてロゴ制作や電子見積書・請求書システムの導入も検討しましょう。
ステップ7:受注ルートの確保
安定的に案件を受注するためには、元請・同業ネットワークを活かすとともに、紹介媒体や職人向けマッチングサイトへ登録して案件の入口を広げることが重要です。
ここまでの準備には最低3か月、余裕を持って半年を目安に逆算スケジュールを組むとスムーズです。
独立直後は「どこから仕事を取るか」でつまずきやすいポイントです。
具体的な案件獲得方法については、以下の記事で詳しく解説しています。
どれくらいの資金が必要か? 独立初期費用について
独立初期費用を具体的な数字で把握することは、必要以上の借り入れを避けてスムーズに事業を立ち上げるために欠かせません。ここでは、独立に必要な主な経費とそのおおよその目安を紹介します。
独立時に必要な「初期投資」一覧
次の表を踏まえ、100万〜300万円を初期費用の目安とし、計画的に資金を確保しましょう。
|
項目 |
目安費用 |
備考 |
|
工具・機材購入 |
30〜100万円 |
|
|
作業車両 |
中古50万円〜/新車200万円前後 |
移動・搬送用のバン・トラックなど |
|
保険加入費 |
年間5〜10万円 |
労災・賠償など各種保険 |
|
事務所開設費 |
自宅兼用はほぼ無料/賃貸は敷金礼金+内装費 |
机・PCなど備品含む場合あり |
|
登録・各種手数料 |
3〜4万円前後 |
登録電気工事業者の申請手数料(約33,000円)+収入印紙代・郵送料など |
なお、独立に必要な初期費用は、補助金や助成金を活用することで大きく抑えられる場合があります。
月々の固定費とキャッシュフローの目安
固定費に加え、材料仕入れ分の立替や税金も考慮したうえで「3か月分の運転資金」を手元に用意しておくと安心です。
|
項目 |
目安費用 |
備考 |
|
車両維持費 |
3〜5万円 |
燃料・保険・駐車場など |
|
通信費 |
約1万円 |
スマホ・インターネット回線 |
|
保険料 |
5,000〜10,000円 |
業務災害・賠償責任保険など |
|
借入返済 |
個別に異なる |
初期投資に伴うローン返済額 |
一人親方として独立するデメリットとは
独立は自由と高収入の可能性がある一方で、リスクと責任も伴います。そのため、前述したメリットに加え、デメリットも理解しておくことが大切です。
具体的には、次のようなデメリットを頭に入れておきましょう。
- 売上変動リスク … 受注が少ない月は収入が激減する恐れ。
- 全責任を負う立場 … 品質・納期・クレーム対応まで自己完結が必要。
- 営業・経理など現場以外の業務も必要 … マルチタスク力が求められる。
一人親方として安定して仕事を得る方法
独立するために実績と技術力が必要なのはもちろんですが、それだけでは案件を継続して受注することは難しいでしょう。
営業力と情報発信を組み合わせ、複数のルートから安定的に受注を確保できる体制を整えることが大切です。
具体的には、次のように人脈・元請企業・紹介媒体を活用することが求められます。
- 前職でのネットワークの維持 … 元同僚や取引先との関係を良好に保つ。
- 業者間ネットワークの構築 … 資材屋・設備業者・同業者と情報交換。
- 専門マッチングサービスの活用 … 職人と業者を結ぶマッチングアプリ等を使い案件を拡大。
一人親方としての独立に関してよくある質問
Q1. 独立に必要な資格は何ですか?
A1. 最低でも第二種電気工事士が必要で、より大規模な工事を請け負う場合は第一種が求められます。いずれの場合も目安3年以上の実務経験を証明する書類が必要です。
Q2. 開業までにかかる期間はどのくらいですか?
A2. 事前準備から登録完了まで最短3か月、余裕を見て半年ほどが一般的です。書類の不備や車両・工具の納期によって前後します。
Q3. 独立初期に必要な資金は?
A3. 工具・車両・保険・事務所などで総額100万〜300万円が目安です。さらに固定費3か月分の運転資金も確保しておくと安心です。
Q4. 仕事を安定させるコツはありますか?
A4. 前職や同業とのネットワークを維持しつつ、Webサイト・SNSなど複数の受注ルートを持つことが大切です。
仕事が増えてくると「一人では回らない」という壁に直面することもあります。
独立直後に多い“人が採用できない問題”については、こちらの記事も参考にしてください。
事前準備をしっかり進めて、一人親方としてのリスクを減らそう
ここまで、電気工事士の方が一人親方として独立するために必要な準備について解説してきました。
そうした準備はもちろんですが、独立後に継続して案件を受注し、成長していくためには、業界事情についての理解を深めておくことも重要です。
電気業界専門の求人サイト「電工ナビ」では、無料でダウンロード可能で、業界事情がすぐ理解できる資料を複数用意しています。
ぜひ、下記よりダウンロードいただき、ご一読ください。
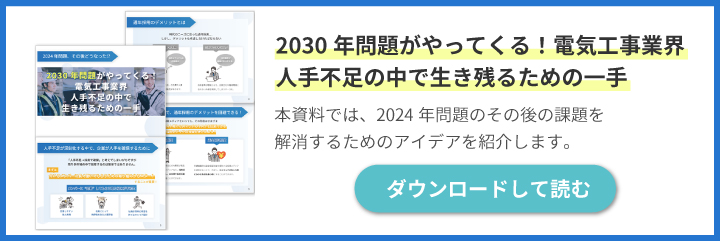
【情報提供元】